 心理
心理 自分が超人ではないことを知り、かと言ってダメなわけではないことも知っておく
夢を見すぎてバランスを崩してはいけない。自分が超人ではないことを知り、かと言ってまったくダメなわけではないことも知り、その上でできる限りの可能性を探っていく。そうやって現実を直視して生きるのは役に立つのだ。きちんと現実を直視する能力が自らを...
 心理
心理  心理
心理 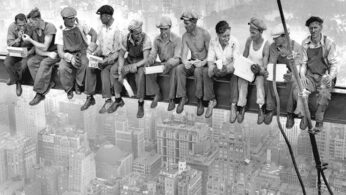 心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理  心理
心理