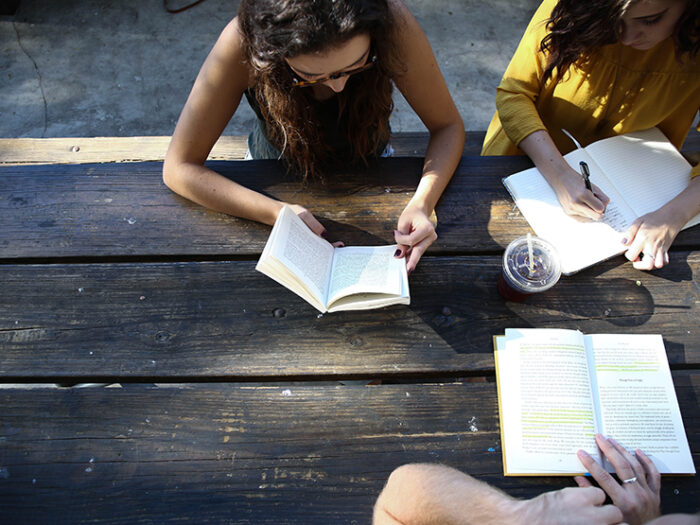
継続しなければスキルや知識は身につかない。一日で覚えたものは継続しなければ、だいたい忘れる。何かをはじめたとき、最初から目的のものがすんなりと手に入るほど世の中は甘くない。「継続は力なり」だ。だが、この「継続は力なり」には、あまり意識されていないワナがある。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。著書は『ボトム・オブ・ジャパン』など多数。政治・経済分野を取りあげたブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」を運営、2019、2020、2022年、マネーボイス賞1位。 連絡先 : bllackz@gmail.com
「継続は力なり」の意識されないワナとは?
「継続は力なり」という言葉がある。これは、目的を達成する前に早々とあきらめる人を戒め、つらくても継続することに意味があると知らしめる格言である。
継続しなければ、スキルや知識は身につかない。一日で覚えたものは、継続しなければ3日後にはだいたい忘れてしまっている。何かをはじめたときに、すぐに目的のものがすんなりと手に入るほど世の中は甘くない。
継続することで、必要なものが身につく。
私たちが新しくはじめたものというのは、だいたいは一度では覚えられずに失敗し、ときには反復しても身につかずに挫折し、新たな技術や知識を身につけるために、けっこう苦労したりする。
継続するというのは、まさにそうした失敗から学び、間違いからも気づきを得て、身につけていくということなのだ。継続して学べば学ぶほど、何でも上手になる。そして、何とかうまくできるようになってくると、それが自信につながる。
その自信が、その後の人生において、多くのことを成し遂げるための原動力になり、困難を乗り越える燃料となる。
しかし、この領域にまで到達するのは、非常に気力と忍耐がいる。だからこそ、継続は力なりという言葉があって、人々を「すぐにあきらめるな」と戒めている。
「継続は力なり」という言葉は、努力によって自分を成長させるものであり、だからこそ無条件に賞賛されている言葉でもある。それはいいのだが、そこに「あまり意識されていないワナ」があることには気づく必要がある。
ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。
目標を達成するための条件が揃っていない
「継続は力なり」の意識されないワナとは何か。それは、やってみて違うと思ったことであっても、「継続は力なり」と考えて惰性で続け、結果的に実りのない状況に陥ってしまうことだ。
「やってみて違う」というのは誰でもある。人間は超人ではない。努力しようが何だろうが「自分には向いていなかった」というケースは多い。努力する以前に「目標を達成するための条件」が自分には揃っていないのだ。
肉体的な能力が備わっていない。遺伝的能力・才能が備わっていない。目的に到達するのに時間がかかりすぎる。それに本気になれない。自分が心から目指しているものではない……。
こういった場合、いくら「継続は力なり」といっても充実感は得られない。肉体的・遺伝的に到達できない目標である場合、継続は自分を傷つけていく。やっていることが自分の世界ではないとわかっているのに継続するのはストレスもかかる。
難しいのは、最初からそれがわからないことだ。やってみて、はじめて気づく。
たとえば、絵に関心があって画家になりたいと思ったとする。それに取り組む前は、自分に絵の才能と情熱があるかどうかはわからない。それでやってみる。そうすると、しばらくして自分が没頭できるものかどうかわかってくる。
真剣にやってみて、その結果、どうも自分に向いていないと思ったり、続けることに違和感を感じたり、関心を持てないと思ったり、才能もないと思ったり、やりたいというエネルギーも消えたことに気づいたりする。
それでも、「継続は力なり」を当てはめるべきだろうか?
「自分には向いていなかった」という事実があきらかになったのであれば、そこから手を引くほうがいいのではないか。
最初は、誰でもいろんなものに挑戦し、試行錯誤する。それで自分の目指すものではないとわかった場合、それにも「継続は力なり」と思って我慢していたら、それこそ時間の無駄だ。
インターネットの闇で熱狂的に読み継がれてきたカンボジア売春地帯の闇、『ブラックアジア カンボジア編』はこちらから
枝葉を切り取らなければ、選択も集中もできない
ということは、「継続は力なり」の一方で、自分の世界ではないと思ったことには「さっさとやめる」という決断も重要であることがわかる。「続ける」という決断の裏に、「やめる」という決断も必要になる。
自分に向いていないもの、関心のないもの、自分の人生に必要のないもの、好きになれないもの、意味のないものを継続している場合、それをやめる。
ほかの人にとって、それは重要かもしれない。だが、自分にとって重要でなければ、やめるのは悪い選択肢ではない。自分にとって重要ではないと思えば、遅かれ早かれ、そこから離れていくことになるからだ。
よけいなことを「やめる」ことによって、本当に必要なことに集中できる。それによって人生がシンプルになる。迷いもなくなる。どうでもいいものを「やめる」と、それだけで時間も、情熱も、資金も、重要なものに集中させることができる。
なんでもかんでも、ただ続ければいいというものではない。
優れた企業はつねに選択と集中をして、自社に見合わない部門を切り捨てるが、この「選択」と「集中」は、どちらも一点に全力投球する行為であることに気づかなければならない。
選択と集中を実現するためには、どうでもいいものをすべて「やめる」しかない。中途半端な人がいう「やめる」と、選択と集中に取り組んでいる人がいう「やめる」とは、同じ「やめる」でもまったく意味合いが違う。
「継続は力なり」という言葉は、多くの人にとって努力の継続を支える励ましの言葉になっている。ところが、この言葉を誤解して盲信した場合、かえって自身の成長や成功を妨げる結果につながっていく。
1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから
あなたは、やめる勇気、引き返す決断ができるか
継続が目的化すると、本来の目標を見失うことがある。たとえば、スキル習得のためにはじめたものが、いつのまにか「やめることは悪いことだ」と感じる心理的な負担に変わることがある。
このような状況では、目的や意義が失われているのに、ただ続けているだけの状態に陥る。結果として、やりがいや充実感を感じることが難しくなり、モチベーションの低下につながる。
やめるというと、失敗したと思われる。格好が悪いと笑われることもある。挫折したと陰口を叩かれることもある。力がなかったと思われることもあるし、ときには中途半端だと罵られることもある。
とはいっても、それが自分の目指すものではないと途中で気づいたら、逆に毅然と決断しなければならない。継続の意味がないと理解したとき、「やめる」ことで次のステージに移ることができる。
プライドが傷ついて、やめなければならないのにやめれない人もいる。しかし、プライドごときで時間も金も消耗して撤退を迫られるより、他人にどう思われても、毅然として「やめる」という勇気が必要なのだ。間違った「継続は力なり」は、次のような問題が発生する。
・思考停止に陥る危険性
・目的を見失う危険性
・モチベーション低下の危険性
・機会損失の危険性
・ストレスの蓄積の危険性
・自己評価低下の危険性
・成長停滞の危険性
あなたは、やめる勇気、引き返す決断ができるだろうか。もし、熟考した結果、やめるべき事柄であった場合は、杓子定規に「継続は力なり」を当てはめず、まずはゆっくり休み、よく考えたほうがいいのかもしれない。
自分の人生にとって重要ではないものに「継続は力なり」という格言を当てはめてはならない。自分にとって重要なものに選択・集中して、必要ないものは毅然と「やめる」のが重要だ。「継続は力なり」は重要だが、その使いかたを間違ったら人生に破滅をもたらす。
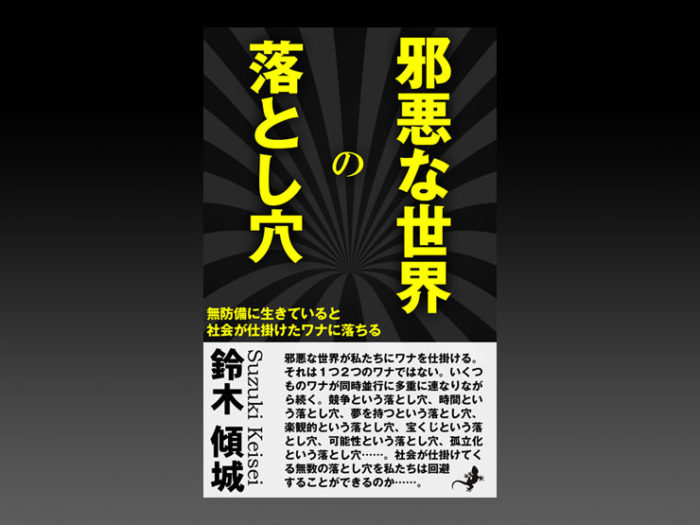




コメント