
政府、企業、家族……。かつて私たちを守ってくれていたものは、もう機能していない。誰も私たちを守ってくれなくなった。だから、私たちはひとたび坂道を転がり落ちると一気に貧困化することになる。この残酷な事実を認識するのは重要だ。こんな世界で私たちは生きている。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
今の時代、「政府が何とかしてくれる」と思ったら大間違いだ
日本社会は1990年のバブル崩壊以後、急激に変わっていった。どのように変わったのか。人々が頼りにしていたものが、頼りにならなくなっていったのだ。
時代が変わり、今まで「自分を守ってくれていたはずのもの」が、自分を守ってくれなくなっていた。ところが、人々は時代が変わったということに気付かず、まだ「自分はこれで守られるはずだ」と思い込んでいる。
その思い込みが落とし穴になっていて、足を踏み外して落ちたところが格差社会と貧困地獄だったのである。社会が変わったことによって私たちはもう誰も守ってくれないということを意識しないといけない。
「政府が何とかしてくれる」というのも幻想だし、「企業が何とかしてくれる」というのも幻想だ。 そして家族の絆が薄らいで単身世帯も増える中では「家族が何とかしてくれる」というのも幻想になっている。
もはや、政府も企業も家族も頼れない世の中なのである。
まだ「国民が困ったら政府が助けてくれる」という幻想にすがっている人もいるが、もうそんな甘い考えは捨てた方がいい。
日本がまだ曲がりなりにも成長していた1980年代までは、確かに助けてくれただろう。しかし今は違う。
税金ひとつ取ってもそれは分かる。政府は税金の引き上げに本気になっている。税金と言えば消費税にフォーカスされることが多いが、取られる税金はそれだけではないのだ。
政府は所得税を取り、住民税を取り、固定資産税を取り、国民年金を取り、介護保険料を取り、自動車税を取り、ガソリン税を取り、酒税を取り、タバコ税を取り、贈与税を取り、相続税を取って、ひたすら国民からカネを毟り取る。
今やサラリーマンの税金負担は年収の50%に到達しようとしている。給料をもらっても半分は税金で飛ぶ。これを搾取と言わずして何を搾取と言うのか。
「政府が何とかしてくれる」と思い込むのは危険だ。「何とかしてくれる」どころか、経済的に私たちの足を引っぱる元凶になりつつある。コロナ禍を経て、政府はますます混迷しつつある。今後も税金の引き上げによる国民搾取は過酷になっていくばかりだろう。
ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。
企業のあこぎな経営のツケを私たち国民が払っているのだ
「政府が何とかしてくれる」と思い込んだら、思いきりアテが外れる。政府の施策を待っていたら、間違いなく貧困の落とし穴に堕ちる。頼りにならないものを頼りにしても仕方がない。
では、「企業」が何とかしてくれるのか。いや、企業が何とかしてくれていたのもバブル崩壊以前の話だ。
1990年代のバブル崩壊で日本企業は土地という担保の極度の目減りで資産に大ダメージを受け、さらに1989年から取り入れられた消費税によって消費までもが減退して、企業体力は急激に消えていくようになった。
それが顕著になったのが1990年代後半から2000年代初頭である。企業は激甚化していく競争に打ち勝つためにコスト削減と経営効率化を進めるようになっていった。
具体的に言うと、企業は正社員を減らして非正規雇用を増やし、給料を削減し、年功序列も終身雇用も止める方向に向かったのだ。さらに企業は低賃金・悪条件で働く人材を求めて、海外から安い労働力を入れるようになった。
外国人の労働者を日本国内で大量にこき使うので日本は外国人だらけになる。だから企業は「多文化共生」みたいなものを日本人に押しつけるようになっているのだ。
多文化共生は「きれいごと」である。私たちがしっかり把握しておかなければならないのは、この多文化共生というものは、企業が労働者を低賃金・悪条件で働かせようと動いた結果だということだ。
企業のあこぎな経営のツケを私たち国民が払っているのである。
企業がやっているのはそれだけではない。利益を極限まで増やす一環としてハイテク化・人工知能化・ロボット化も進んでいくわけで、日本人の雇用はどんどん消えていく。それが未来の光景なのである。
このような状況なので日本人は事あるごとに切り捨てられていく。企業はどんどん身軽になっていくのだが、だからこそ「企業が何とかしてくれる」と思ったらハシゴを外されるのだ。
経団連も「終身雇用は維持できそうにない」と公然と言うようになってきている。終身雇用が維持できないというのは、要するに時期が来たら従業員を切り捨てるということに他ならない。
インターネットの闇で熱狂的に読み継がれてきたカンボジア売春地帯の闇、『ブラックアジア カンボジア編』はこちらから
「家族が何とかしてくれる」というのはもう幻想に過ぎない
企業がコスト削減のために人を抱えないようになっており、そのための技術革新も急激に進んでいる。そのため、そこらへんの大学に入って「大学卒」の学歴を持ったところで意味がない。
名門大学に入って官僚になったり一流企業に就職する一部のエリートのコースはまだ意味がある。
しかし、普通の大学かそれ以下の大学に入って普通の企業に勤めるような生き方は、将来をまったく保障してくれない。もう大学卒みたいな「学歴」に頼って生きるのは、賞味期限が切れている。
まして、莫大な奨学金という名の借金を背負って大学を卒業するという行為にはほとんど意味がない。「学歴が何とかしてくれる」という無意識が落とし穴なのだ。
ここに気付かない人が大学を卒業して「この学歴も借金も何にも意味がなかった」と愕然としながら、細々と借金返済の人生を送ることになるのだ。
まだあどけない二十歳前後の若者に、数百万も借金を背負わせる親はどうかしているし、こんな状況に突き落とす高校の教師も大学の教授も恥を知るべきだ。
教師は学生の将来を真摯に考えるのが仕事ではないのか。それとも、教え子に借金を背負わせるのが仕事なのか。若者を借金地獄に突き落とす残酷な仕打ちはいい加減にやめるべきだ。
世の中の何にも頼るものがないのであれば「家族」に頼るしかないのか。まさか。個人主義を取り入れ、家族の絆も弱まっている現代の日本では、もう「家族」も頼りにならなくなっているのだ。
親の世帯が貧困化すると、子供たちを援助したくても援助できない。さらに今の若者は親に対しての関係がドライになっているので、家族であっても他人のような関係になっている。
これが突き進めば「親が経済的に困っても関係ない」と思う子供が増えるし、当然だが親の方も「子供がどうなろうと知らない」という考え方になる。そうやって親子の関係は希薄になり、家族はバラバラになる。
「家族が何とかしてくれる」というのはもう幻想に過ぎない。家族の絆は私たちが想像している以上に空虚なものになってしまった。
政府、企業、家族……。かつて私たちを守ってくれていたものは、今の時代はもう機能していない。誰も私たちを守ってくれなくなった。この残酷な事実を認識するのは重要だ。こんな世界で私たちは生きている。だから、私たちはひとたび坂道を転がり落ちると一気に貧困化することになる。
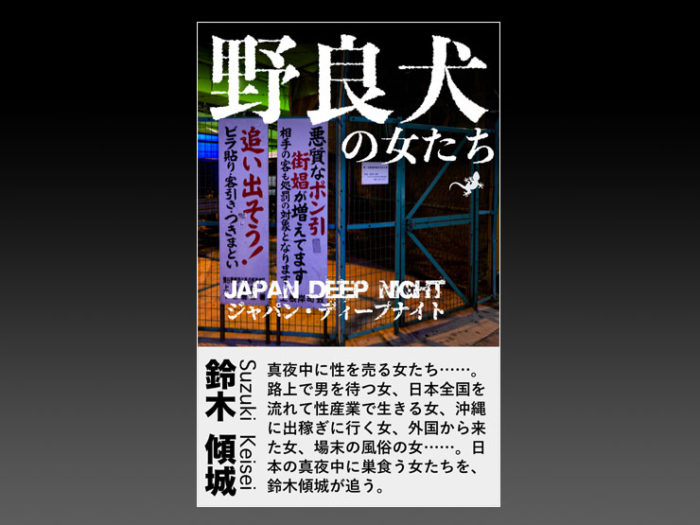




コメント
邪悪な時代は、弱いものを見捨てる人間が笑って勝つんでしょう。
そういう人間は生まれつきそうなんでしょう。
見捨てられない人間は仕方ありません。どんなに不利でも自分で選んだわけではない生まれつきは変えられない。邪悪さや無情さに苦しむ自分の人生を引き受けるのみです。
例えば孤立の中、優しさや愛情ゆえ弱い家族を引き受け看護すれば大体の人は心身をすり減らしていきます。
でも、今のところまだ、この社会では家族を引き受けただけでは社会から直接的な死刑やリンチにはあわない。
金銭的な厳しさ、心身の疲労、絶対的な不利と孤立と社会的尊厳のなさに消耗していくだけで、いきなり殺されはしない。それだけでもまだ幸運かもしれません。
私の昔の縁者姻戚は、子供の病気や障害を理由に私と子供を見捨てました。だのに私は誰も助けない時代に進む中でも、自分の子供を捨てない選択をしてます。今のところ。見方を変えると、まだ捨てないでいられる、それでも食えている幸運の中にあるとも言えますが。
こういう人間は弱者切り捨ての時代に即してないから苦しむんでしょうね。
適者生存の原則から見れば弾かれるしかない。
時代の寵児になるのは難しいものです(笑)
弾かれながらでも私は(子供の生存のため)生きるぞー…いや、生きていけたらいいな…うん、生きていけるよう頑張るから…生き残れますように(ヤバい。最後は祈るしかなくなった)
邪悪と闇に焦点を当てまくるブラックアジアは邪悪の時代こそもっと元気に生き残れますように…!(だって読むのが楽しみなんだもん!)
(これもヤバい最後は祈るしか後略)