
2020年代に入っても、人間は偉くなったわけではない。偉くなるどころか、むしろどんどん短絡的かつ近視眼的になっているように見える。理由はある。世の中はますます弱肉強食の資本主義の姿を見せるようになっていて、企業も国家も「自分の利益」を極大化させることを強要されるようになっているからだ。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
対処しようと思ったとき、すでに手遅れになっている
人間は将来を考えることができる地球上で唯一の生き物だ。しかし、だからと言って将来の破滅に対して何らかの手を打てるとは決まっていない。
むしろ、破綻が見えながらも、実際にその破綻が目の前にくるまで何もしないことの方が多い。
破綻が回避できると思ってはいけない。むしろ、スケールの大きな集合体になればなるほど、実際に破綻するまで何も動かないことの方が大きい。
巨大な船は目の前に岩があってこのまま直進したら座礁すると分かっていても、急に方向転換することもできないし船を止めることもできない。目の前に障害物が現れた時はすでに手遅れなのである。
国家の目の前に現れる「障害物」はいろいろなものがある。中国は恐ろしいまでの環境破壊・大気汚染が恒常化している国だが、住民の健康が恒常的に破壊され続ければ、いずれはそれが国家の損害になることくらいは誰でも分かっている。
しかし、止まらない。環境破壊・大気汚染の解決にはカネも時間もかかる。だから、極限状態になるまで放置される。本当にどうにかしないといけないほどの状況悪化が来たとき、すでに手遅れになっている。
日本は急激なまでの超少子高齢化が進行して国家の衰弱が起きているのだが、このままでは今の国力が維持できないと誰もが分かっている。しかし、誰も真剣にそれに対応することも問題意識を持つこともない。
だから、破滅の予感、破滅の危機感を持ちながらも、最終的に破滅するまで何もしないで突き進む。本当にどうにかしないといけないほどの状況悪化が来たとき、すでに手遅れになっている。
ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。
「もっといける」という熱狂が支配して理性が働かない
破滅を予感しても、実際に破滅するまで押し流されるという現象は、経済の世界でもしばしば起きる。
たとえば、バブルがそうだ。
いったんバブルが生まれると、大勢の人間がそこに我先へと押しかけて泡を膨れ上がらせる。途中でみんなが正気に返るということはない。
誰もが「これは危ない」と思いながらも、結局は最期まで暴走して、ある日、一気にカタストロフィに見舞われる。
経済史には繰り返し繰り返しバブルの歴史が出てくる。経済史とはバブルが生まれ、崩壊する歴史の繰り返しである。そのすべては馬鹿げた値段まで買い上げられては自壊していく。
「人間は破滅が見えていても止まれない」のだということを知ることができる。
日本もそうだ。1980年代後半には資産バブルが暴走して止まらなかった。それで1989年12月にはバブルの頂点に達し、日本経済の健全性を根こそぎ破壊して現在に至った。
アメリカでもそうだ。1998年から2001年までのITバブルも、崩壊するまで止まらなかったし、2008年9月15日までのアメリカの不動産バブルも大崩壊するまで止まらなかった。
リーマンショックの前から、不動産も、サブプライムローンも危険だと、事前に警鐘が鳴らされていた。しかし、「破滅が見えていても止まれなかった」のだ。実際に、爆発炎上するまで止まらないのである。
買い上げられたものは、いずれは崩壊するというのは誰もが常識で分かっている。ところが、分かっていても止まらない。行き着くところまでいって、崩壊に付き合わされる。
破滅の予感、破滅の危機感を持ちながらも、最終的に破滅するまで暴走してしまう。
後で振り返ると、これはバブルだから降りておくべきだったと解説できるのだが、現場では「もっといける」という熱狂が支配しているので理性が働かない。破滅の予感を感じながらも、目先の欲望にとらわれる。
1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから
誰もが結論が分かっていたが止まらなかった
イギリスは、かつて「7つの海を支配する帝国」だった。しかし、国民が行政に依存することになったせいで、国家の累積債務が膨らむだけ膨らんでいった。
国民が働かなくなった上に、多くの人が既得権益にしがみついたまま離さなかった。その結果、1976年にはとうとう国家破綻(デフォルト)に追い込まれてしまった。
イギリスがデフォルトしたのは1976年だが、「この国はもうダメだ」とは1960年代からずっと言われていたことだ。しかし、予測されていても止められない。
いずれ崩壊すると分かってはいたものの、誰もが国家に頼って何もしなかったし、自分の権利も手放さなかったので、崩壊が免れなかったのだ。本当に破綻するまでは、誰もが最期の日の前日まで「誰かが何とかする」と信じていたのだった。
ロシア(旧ソ連)もまたそうだった。
資本主義を駆逐して共産主義を生み出したソ連は最初はアメリカをもしのぐ技術大国だった。アメリカと競うように核を製造し、宇宙開発に資金を注ぎ込んだ。
ところが、すべてを国営にしたことにより競争力が失われて共産主義が欠陥商品であることが明るみになった。それでもソ連は共産主義を捨てずに最期まで暴走し、結局行き詰まって崩壊していった。
誰もが結論が分かっていたが、最後にクラッシュするまで止まらなかった。
国家崩壊は歴史の話ではない。現在も、世界のあちこちで国家崩壊が起きている。途上国の大半は国家は崩壊したも同然だが、こうした経済崩壊は金融市場がクラッシュするたびに中進国にも波及する。
地獄のようなインド売春地帯を描写した小説『コルカタ売春地帯』はこちらから
「自分の利益」を極大化させることを強要される
これからも、私たちはその光景を目撃することになる。2020年代のどこかで間違いなくそれは起きる。
2020年代に入っても、人間は偉くなったわけではない。偉くなるどころか、むしろどんどん短絡的かつ近視眼的になっているように見える。別の言い方をすれば、人間がどんどん投機的になっており、社会が投機的な動きになっている。
理由はある。
世の中はますます弱肉強食の資本主義の姿を見せるようになっていて、企業も国家も「自分の利益」を極大化させることを強要されるようになっているからだ。
企業は利益を確保できないと経営陣は無能扱いされて株主から吊し上げられる。国家は利益を確保できないと政権が無能扱いされて国民から吊し上げられる。
かつてはひとりひとりの国民の不満の声は、大して大きな声にはなり得なかった。しかし、いまやインターネットやSNSという「不満増幅装置」があって、成果を出せないとインターネットという世論で吊し上げられる社会になっているのだ。
そのため、経営者も政治家も短期的な成果を追求せざるを得ない。それが投機的かつ近視眼的な行動を生み出しているのだ。
投機的かつ近視眼的な行動は、往々にしてリスクの高い行動を誘発する。失敗すると致命傷になるが、成功したら巨大な利益を得られる。危険だが、「不満増幅装置」が動作しているので逃れられない。
かくして、大きな成功を得る企業や国家もあれば、一瞬にして危機に陥る企業や国家も出てくる。
人間は将来を考えることができる地球上で唯一の生き物だが、結局はこうした社会環境が破滅をもたらすと分かっていても、もう止められない。2020年代はリスクが破滅を生み出す社会になるのは必至である。



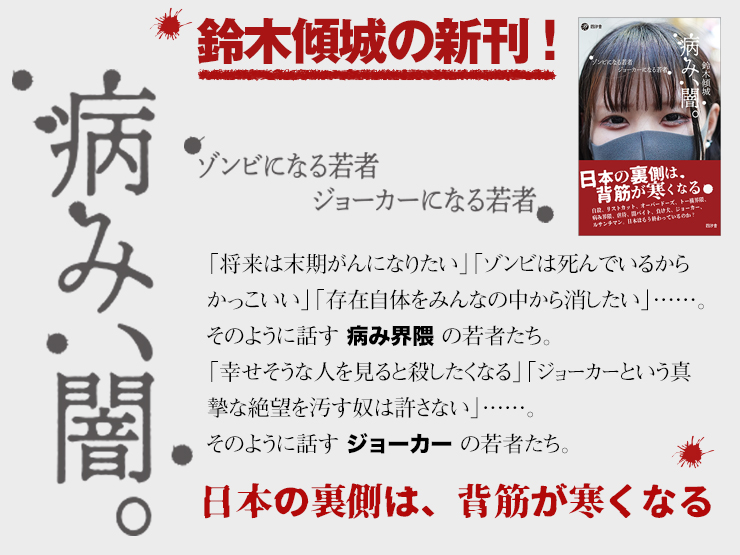






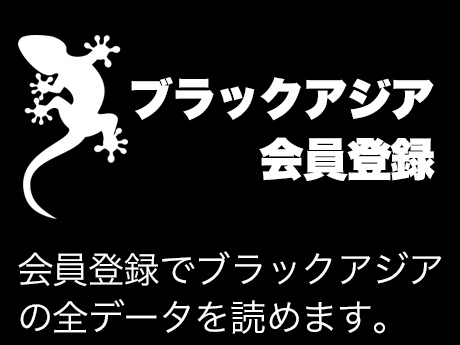



















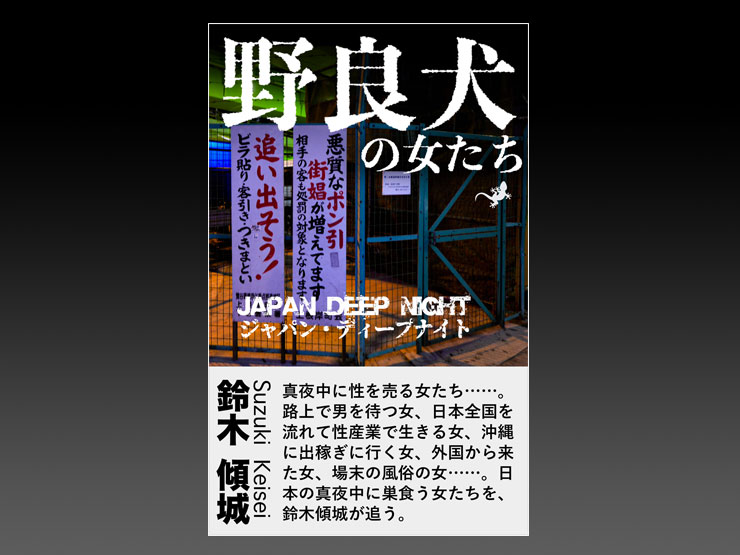










コメントを書く