連載記念特典! この内容は『ブラックアジア 売春地帯をさまよい歩いた日々 タイ編』の中から「パッポンのマイ」を〝全編〟掲載しています。『アジアの暗黒街で愛を探した男』で登場したマイは彼女のことです。会員の方はぜひお読みください。

二十歳《はたち》の頃、何気なくタイへ旅行に行った。はじめての海外旅行でひとり旅だった。見るもの聞くものが何もかも珍しく、旅に有頂天になった。
南国の太陽や文化や食事は慣れれば慣れるほど心地良いものとなってきた。最初は健全な旅行をしていたが、ある日バンコクのパッポンに足を踏み入れた。パッポンはアジアでもっとも有名な歓楽街である。
タイに行ったのなら、ここを訪れないと片手落ちだと思ったのだ。ただ半裸で踊り狂う女たちを見て、話のネタにでもしたかった。
パッポン……。
社会見学のつもりで、恐る恐るゴーゴーバーに向かう。入った店は『リップ・スティック』である。女たちが踊っているのを見ても何も思わなかった。まだ若く所持金も乏しかったので、ぼったくられる心配だけが頭の中を空回りしていた。
楽しもうなどとは、まったく思わなかった。パッポンがどういうところか分かったら、一刻も早くここを出てゲストハウスに戻りたかった。パッポンはぼったくりの横行する怖いところだと聞いていたのだ。早く帰って安全になりたいと、それしか頭になかった。
当時の私は女から女へと渡り歩く浮気な男には、良い感情などまったく持っていなかった。むしろ、セックス・アニマルと陰口を叩かれている一部の日本人旅行者を軽蔑していた。今では信じられないのだが、若い頃は絶対にこんなところへ出入りしたくなかったのだ。
隣に座ってほほえんでくれた娘がいた……
すべすべした肌を持ったきれいな女性だった。「どこから来たの?」と質問されて「日本から」と答えた。次に歳を訊かれたので「二十歳」だとつぶやくと、彼女は顔をぱっと輝かせた。
“Same Same!”(同じね!)
自分と同じ歳の女性がここにいる。しかもヨーロッパ人や日本人やアメリカ人、つまり世界を相手に身体を張って生きている。同い年なのに、彼女は精神的にずっと大人に見えた。
そのことに複雑な感銘を覚えた。そして、柔らかな笑みを浮かべる彼女に興味を持った。もし彼女が二十四歳だとか二十五歳だとかだったら、興味さえ持たなかったはずだ。
たどたどしい英語で言葉を交わし、名前を交換しあった。彼女の名前は「マイ」と言った。今となっては何を話したのか覚えていないが、ずっと他愛のない話をしていたように思う。こちらはほとんど英語ができなかったので、ただ単語を並べただけの会話だった。
言われていることが聞き取れず、戸惑ってばかりいると、彼女はそっと手を握って”I love you.”(アイ・ラヴ・ユー)と言ってくれた。それは「愛している」という意味ではなくて、大丈夫、心配しなくてもいいからね、という優しさが込められているように思えた。
今でもそのときの彼女の表情や言葉や手の感触を覚えている。彼女にはただの営業トークだったかもしれないが、魔法にかけられたかのようにのぼせ上がってしまった。
思えば、この瞬間に人生が狂ってしまったのだ。
そばにいた別の女性が「一緒にホテルへ行けば?」と笑いながら言ったが、それを聞いて驚いて首を振った。 出会ったばかりの女性とホテルに行くなど恥ずかしかったし、とてもそんな勇気がない。本当に、怖かった。
そのあと、逃げるようにして店を出てパッポンを後にした。ゴーゴーバーに行くという「社会見学」は終わり、もうパッポンには用がないはずだった。
しかし、翌日の夜も私はパッポンに行った。店に入るなりマイを指名した。同年代の女の子は、はにかみながらやってきた。募《つの》る想いを彼女に伝えたかったが、いかんせん英語能力がなく、タイ語もまったく分からない。
彼女の手を握りしめ、何かを伝えようとしたが何も言えなかった。満たされない気持ちでその日も引き上げた。その夜ひとりで手持ちの現金を数えながら、明日もう一度行って彼女を連れ出すことを決心した。
そして翌日、ついにマイをペイバー(連れ出し)した。マイは喜んでくれていた。マイと一緒にいられて嬉しかったのを覚えている。パッポンの屋台でバーミーナムを食べてから、マイが教えてくれた安いホテルに向かう。部屋でふたりきりになると、どぎまぎし、うろたえ、どうしていいのか分からなくなった。
異国の知らない娘とふたりで、静かな部屋にいる。
彼女はセックスをするためにここにいる。
彼女のことを何も知らない。
それなのに、彼女を裸にしたり、その身体に触ったりすることが許される。本当にそんなことをしていいのだろうか。こんな状況は初めての経験だった。それは正しいことじゃない。間違っている。そんな思いもずっと頭から離れなかった。そんな緊張が移ったのだろうか。マイまで、すっかり固くなっていた。
罪の意識は感じていたが、目の前の女性のほほえみには抗《あらが》うことができなかった。そして、はにかみながら裸の肉体を抱きしめた。まだウブだったので、彼女との経験はあまりにも鮮烈過ぎた。これで、マイの虜《とりこ》になってしまった。
何度か彼女をペイバーしたが、そのうち金が続かなくなってきた。事情を知ったマイはある日ゴーゴーバーに行かなくなり、朝から晩までそばから離れなくなった。
最初の一週間ほどは有頂天だった。毎日のようにゲストハウスの狭い部屋で一緒にいて、ベッドの上でまどろんでいた。マイは天使のような存在だと思った。バンコクはクルンテープと呼ばれ、それは「天使の都」という意味だというのは知っていた。マイは天使以外の何者でもなかった。
しかし、この幸せはすぐに終わり、徐々に悪い方へと転がり始めた。
マイが部屋から出してくれなかったのだ。
バンコク中をほっつき歩きたかったが、一緒に街を出歩くことさえ嫌がった。また、カオサン・ストリートで他の日本人たちと会うのも許そうとしなかった。そういうわけで、彼女と口論をすることが多くなってしまった。
無理に出かけようとすると、マイは泣き叫びながらすがりついてくる。マイは朝から晩まで部屋でじっとしていることを強いたのだった。彼女は文字通り、ふたりだけの世界を欲していた。確かにそれは素晴らしいことだったが、熱い部屋の中に一日いるのは、つらいものだ。
彼女を振り切ってカオサンに行き、他の日本人と長話をして戻ると、ゲストハウスの外で所在なげに待っていたマイは「女と会ったのか?」と激しく問いつめてきた。
「日本人の友達と会っただけだよ」
「それは、日本人の女なの?」
執拗だった。その執拗さに、だんだんマイが重荷になってきた。彼女が狂ったように愛してくれたのは分かる。しかし、束縛されればされるほど気持ちが冷めた。
実を言うと、マイがだんだん恐ろしくなっていた。その愛はあまりにも一方的だったし、束縛的だったし、おまけにその嫉妬深さは異様だった。今思うと、彼女の愛を真剣に受けとめられなかった自分に非があるのは明らかだ。しかしその時は、とにかく彼女と離れたかった。
ある日、またもや「出かける」「だめ!」のケンカが始まり、とうとう言ってしまった。
「マイ。さようなら。もう君が好きじゃない」
泣き叫ぶマイの声は今でも思い出す。その声を背に荷物をまとめ、殴りかかってくるマイを放り出してバンコクの街に出た。それで終わりだった。マイとはそれから会っていない。もう古い話になってしまった。彼女と会うことは二度とない。
なぜマイは部屋から出たがらなかったのだろうか。
あとになってそれを振り返ったことがある。その頃は深く考えなかったが、今ではそれがよく分かる。外国人と腕を組みながら街を歩く女は、自分が「売春する女」だと宣伝しながら歩いているようなものだからだ。
昔のタイは、今よりもずっと保守的だった。そんなところで若い女性が外国人と一緒に街を歩き、まわりの人々からうしろ指をさされて平気なはずがない。まして彼女は本当に売春で生計を立てている女性であり、うしろ指を指されても反論しようがない。
だからこそ、それは辛いことだったのだ。そんな多感な女性の「心の動き」など分かるはずもなく、彼女の置かれている状況など考えもしなかった。
しかしながら、彼女は仕事を辞めて男に賭けていた。多少の打算があったとしても、彼女は愛してくれたのだ。しかし、そんなマイを自分の心の中で、それをどう受け止めていたのか。
彼女を愛していると思いながらも、実は深層心理の奥の奥で、本当は彼女を「性欲を満たすためだけの女」として扱っていたのかもしれない。そんな風に自分の心を解釈したくないが、客観的に見ればそうなってしまう。
彼女と結婚することなど露ほどにも考えていなかったし、そもそも彼女が結婚の対象になるとも最初から思っていなかったからだ。日本に連れて帰ろうとも思わなかったし、両親に紹介しようなどともまったく考えなかった。
なぜ、そう考えなかったのか。それは最初からまじめなつき合いや結婚が成立するとは考えていなかったからだ。はじめて「売春する女性」に触れ、自分と彼女の間に線を引き、彼女を線の向こう側の人間であると決めつけていたのだ。
これはこちら側がノーマルな世界で、彼女の居る側がアブノーマルな世界という意味になる。はっきり自覚していたわけではないが、自分はノーマルで彼女はアブノーマルだと潜在意識の中で思い込んでいた。売春をするような女は「アブノーマル」であると心の中にあったのだ。
マイと別れたあと、教えられたセックスの深みにはまった。そして、急速に女から女へと渡り歩く堕落した男になり下がってしまった。信じられなかった。何に駆り立てられているのか分からず、自分を見失った。
自制できなかった。
するつもりもなかった。
つまり、自分は最初からまともな人間ではなかったということなのか……。もしノーマルとアブノーマルを分ける一線があったとすると、実は自分こそアブノーマルの側にいる人間だというのがはっきりしている。
いくら言葉を飾っても、女性を金で抱いているのが現実だ。買う側の男は、買われる側の女よりも数十倍もタチが悪い。何しろ、買われる側は受動的だが、買う側は能動的なのだから。
若かったとは言え、自分がノーマルでマイがアブノーマルな世界にいたなど、よくぞ恥ずかし気もなく思ったものだ。どうかしていた。厚かましいにもほどがある。売春する女性がアブノーマルというのなら、その女性を買う人間はアブノーマル以下ではないか。
ある日、ひとりになったとき、自分のやっていることを振り返って、どうしてここまで堕ちたのかと涙がとまらなかった。野獣《けだもの》になってしまった……。
その後、売春に関わる多くの女たちとつき合って話をするうちに、彼女たちが一様に不幸を背負って生きていることに気がついた。人間、誰しも不幸や不運を持っているが、彼女たちの不幸はあまりにも直接的で剥《む》き出しだ。
親に売られたり、貧困で生死をさまよったり、男に騙されたり、レイプされたりして身も心も傷ついたりしている。教育も受けられず、計算もできない女が最終的に行き着いたところが、夜の世界なのだ。
そういう不幸の中を淡々と生きている女性たちを「アブノーマルな側にいる人間」などと言えた義理ではない。しょせん、タイの売春地帯では、日本人など金を持っている異国のケダモノ以外の何者でもなかったのだ。いつしか「売春婦」と呼び捨てられる女性を前に、傲慢であったことに気がついた。
マイとの別れは今でもほろ苦い想い出として甦る。
今、マイと再会できるものなら再会したい。あの頃はまだ若かったし、思慮が足りなかった。本当にすまないことをした。別れるとしても、もっとスマートな別れ方があった。
実を言うと、今はマイがとても懐かしい。いつも彼女の気持ちを踏みにじった後悔と共に、彼女のしぐさや一緒に過ごした短い日々のことを思い出す。夢にも見る。一度や二度ではない。夢の中では彼女と何気なく自然に雑談をしており、はっと目を覚ましてリアルな夢にしばし呆然とする。
しかし夢はあくまでも夢だ。
今、彼女はどうしているのだろうか。どこで何をしているのだろうか。きっと結婚して子供も数人いるに違いない。幸せになっているのだろうか。結婚したのだろうか。子供たちに囲まれて、もはや「あの時の日本人」など何も覚えていないかもしれない。
そう言えば、彼女の出身地を聞いていなかった。チェンマイ出身なのか、イサーン出身なのかも知らない。両親は健在なのか、兄弟姉妹がいるのかも知らない。考えてみれば彼女のことなど何ひとつ知らないままだった。
そのくせ、彼女はいまだに脳裏から消えることのない想い出としてしっかりと影響力を保ち、自分のその後の人生をじっと見つめているようだ。
マイとの一件以来、どんなに多くの女と出会っても、そしてその女性とどんなに波長が合ったとしても、深入りはしなくなってしまった。彼女たちと刹那的に出会い、未練を断ち切って「さよなら」するのがライフ・スタイルになってしまったのだ。
仕事を辞め、出かけようとする男を必死で押しとどめようとするマイの姿や声が、どうしても脳裏から離れない。それは身勝手な男に賭けた女の哀しい姿だった。彼女を傷つけたのは、他の誰でもなく自分だ。マイと一緒に過ごした日々は実に濃密な時間だったが、その濃密さが心の傷になった。
過ぎ去りし日の切ない想い出だ。
(インターネットの闇で熱狂的に読み継がれてきたカンボジア売春地帯の闇、電子書籍『ブラックアジア タイ編』。他にも多くの出会いと別れが記録されております。ぜひ、お読みください!)


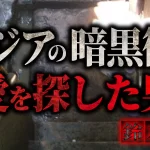

コメント
何度も読んでいる記事ですが、改めて「なぜ自分は歓楽街に居場所を見出してしまったのだろう」と考えてみました。(お話とは別方向ですが、ハイエナになった発端という共通点でお許しください)
分かったのは、私はまだ十代の頃から「夜の街」を見て回るのが好きだったということでした。綺麗事を言うつもりはないので、そこに女性がいること、売春を通してそうした女性と刹那の時を過ごすことも大切で欠くことのできないものです。が、それだけなら日本流のスナックやキャバクラに行ったりエスコートサービス(デリヘル)を使ったりすればいいのに、それは大して好きでないというか興味がわかない。タイでもマッサージパーラー(日本で言うソープランド)に行きたいと思わない。
東南アジアの歓楽街がいいのは店の出入りも気軽で好きなように夜の街を歩ける、そこに女性がいることでその楽しさが倍化する、そういうことなのだと思います。知らなかった女性と出会い、なにがしかの関係を築いたり消失したりするのも夜の街だからこそ拘っているように思えます。
もちろんそこにはたくさんの光と陰があります。いい体験も悪い体験もします。虚飾の中でもほんの少し心が通ったりすることが宝物のように思える一方、性欲を満たすという即物的な充足感も欲しがっています。賑やかな一方で、いろいろなところからくる重苦しさもそこにはあります。でも、それらをすべて込みで自分にとっての夜の街があるのであり、自分にとってはそれこそがいつまでも身を置いて眺めて飽きないものだったようです。それがタイやカンボジアにあった。そこにいる彼女らはもちろん大半が来たくて来ているわけではないから少しでも優しくしようと思うだけで手荒に扱うなど考えられない。それも自分がいたい夜の街の主役である彼女らへの申し訳なさから来ているのかもしれない。
自分がこうなったルーツのようなものがはっきりした一方、どうにも叙情的ではないですね。でも、もし自分の発端に甘い出会いと辛い別れがあったなら早々に歓楽街から足を洗っていたように思います。逆に夜の街に生涯惹かれ続けている限り、死ぬまで変わらない気がしてきました。 (ky)
マイさん自身は、よく白人が幼子を連れて歩いている 契約期間結婚というつもりだったのかなあ とも思いましたが
果たして
強烈な体験だったのですね、男と女は難しい
どこでどう好きになったり惚れ込んでしまったり
所詮生理現象のひとつなのか
本記事、読みました。
古い記事ですが、ブラックアジアの原点と傾城さんの原点を垣間見た気が致します。