
アスペルガー症候群の人の特徴は、とにかく「対人関係がうまくいかない」ということに尽きる。もともと「相手の気持ちが分からない」ので人間関係を後天的に学習するのだが、人間というのは型にハマっているわけではないので学習した通りの区分けができない。その上、自分自身の振るまいも分からないのでどうしても対人関係にエラーが発生してしまう。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
「教育不能」とレッテルを貼られて放逐された子供
1939年秋、政情不安に揺れるオーストリアの生活支援施設にひとりの少年がやってきた。「フリッツ・V」と呼ばれた6歳の子供だったのだが、小学校で当日に「教育不能」とレッテルを貼られて放逐され、施設に放り込まれたのだった。
問題児だった。知能には問題あるように見えなかったが、行動が常軌を逸していた。常にうろうろしていて先生の命令をまったく聞かず、何かのモノをつかんでは壊そうとしたり、引き裂こうとした。
歩き方も発声もどこか奇妙で普通ではなかった。フリッツは何が正常なのかが分かっておらず、歩き方も態度も自分流で通していたのである。
話し方はいやに大人びていて語彙も豊かだった。しかし、その場に相応しい話し方、話題を選ぶことがまったくできずにすべてをぶち壊していた。
他人に関心を持たなかった。他の子供たちと遊ぼうともしなかった。見知らぬ子供がやってきたら殴りかかろうとした。そのくせ、自分の気に入った子供が来たら、相手がどのように思っているのかおかまいなしに抱きつこうとした。
しかし、知能に問題があったわけではない。問題あるどころか非常に優秀で数学は特に強かった。
この奇妙な少年を預かり、観察し、性格の矯正を試み、治療教育を行ったのがハンス・アスペルガーという小児科クリニックの医師だった。アスペルガーは生活支援施設やクリニックに連れてこられる子供たちの一群に、ほんの少数だが「フリッツ・V」と同じ症例を持った子供がいることに気づいた。
以後、アスペルガーはこうした社会不適格な子供たちを200人近く観察し続け、論文を発表した。このアスペルガーの書いた論文が、後に多くの医学者に読まれるようになり、こうした子供たちがいるということが社会にも広まることになった。
知能は問題ないのに社会的に不適合な子供たち。こうした子供たちは「アスペルガー症候群」と呼ばれるようになった。アスペルガー自身は「自閉的精神病質」と呼んでいた。
ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。
学校では問題行動ばかりが目立ち、評価されることはない
ハンス・アスペルガーが観察した子供たちは極度に人間関係が苦手だった。人とうまく関わり合うことができないのである。自分の言いたいことが相手に伝わらない。何かを言っても話がずれていてしばしば相手を当惑させる。
もちろん、両親や親ともうまく関係が築けない。ただ、親は自分の子供が奇妙ではあるながらも、非常に切れ味鋭く恐ろしいほど明晰な頭脳を持っていることを日常で知って、この奇妙な子供を強く評価する。
あまりにも問題行動の方が強いと親も子供が手に余るようになるが、普通ではないとしても、知恵遅れだとか自閉症だとは絶対に思わない。
ところが、学校では問題行動ばかりが目立つので、明晰な頭脳がひらめく瞬間があったとしてもまったく評価しない。完全に落第児であり、問題児であり、社会不適格児として扱われる。
学校は集団行動が必要とされる場なので、そこができていないと先に進まない。アスペルガー症候群にもレベルがあって、叱責や体罰で何とか集団生活に落とし込める子もいれば、それでも難しい子もいる。
どうしても集団生活が難しい子は排除されることになるのだが、何とか集団生活を強制できそうな子に対してはそのまま問題児として通常教育が施される。
アスペルガー症候群の子供たちは頭脳は明晰だ。数学に対して独自の理解を持っていたり、国語に対しても深い分析力がある。
しかし、彼らは学校のカリキュラムに関心を示さず、独自の関心を追い求める性質があるので成績は決して良いわけではない。教えた通りにやることもない。完全に「我が道をいく」のである。成績の良し悪しそのものが彼らの関心外であることも多い。
頭脳が明晰であっても社会的な適応能力が欠けているので、良い学歴を得ることができない可能性が高い。
しかし、アスペルガー症候群の持つ子供の奇妙さは、まわりの教育や辛抱強い矯正によって大人になっていくと「ある程度」は抑制されていき、最終的には知的な職業に就くということもあるとハンス・アスペルガーは報告している。
1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから
集団生活ができない。他人が自分の世界に入り込むことを嫌う
アスペルガー症候群の人の特徴は、とにかく「対人関係がうまくいかない」ということに尽きる。
もともと「相手の気持ちが分からない」ので人間関係を後天的に学習するのだが、人間というのは型にハマっているわけではないので学習した通りの区分けができない。その上、自分自身の振るまいも分からないのでどうしても対人関係にエラーが発生してしまう。
そして「社会性」にも問題を抱えている。まずは、集団生活ができない。他人を自分のプライベートに入れるのを極度に嫌がる。
中には誰かと一緒に食事をするということ自体も拒絶する人もいる。たとえば、デンマークの哲学者であるキルケゴールはアスペルガー症候群だったが、人間関係が壮絶的に駄目で、食事すらも誰かと一緒に取れなかったタイプだ。
決まり事に従うのも心の中では非常に大きな反発心と拒絶心があって、往々にして社会的な道徳にも従わない。
アスペルガー症候群のもうひとつの特徴は「こだわり」だ。アスペルガー症候群の人は普通の人には理解できないものにも執拗かつ粘着的にこだわりを見せる。そして、自分の「こだわり」のみを反復し続ける。
行動パターンに対する固執、同じであることに対する固執、ひとつのテーマに対する固執が尋常ではないレベルで行われる。極度な偏食もアスペルガー症候群の特徴だ。ある狭い境域に対しては取り憑かれたような興味を示して、逆に他のことは何も関心を示さない。
こだわっている関心が社会に役立つことであれば素晴らしく優秀な業績を残すことになるのだが、本人は社会的名誉で関心を決めているわけではないので、はたから見ると「いったい、なぜこんなものにこだわるのか」というものにこだわるのも珍しくない。
たとえば、「蚤(のみ)はどのような種類があるのか」とか「石ころやどんな種類があるのか」とか、そうしたものに異常にこだわることがある。こだわりは色にも、形にも、音にも、天体にも発揮される。
歴史的人物に異常にこだわってリスト化する人もいれば、特定の乗り物にこだわる人もいれば、自分の空想にこだわる人もいれば人それぞれだ。
いったん何かにこだわると、そのこだわりはおおよそ常軌を逸したレベルとなる。(ブラックアジア:ヘンリー・ダーガーは部屋に閉じこもって何を生み出したか)
インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから
大人になるにつれて、自分のおかしさを自覚するようになる
アスペルガー症候群に関しては、研究が進むにつれていくつかのタイプがあることが知られるようになってきた。
・積極奇異型
・受動型
・孤立型
「積極奇異型」というのは、他人に関わることが好きで、非常に積極的で一見「アスペルガー症候群に見えない」のだが、話し出すと一方的で知性をひけひらかし、自分の関心だけをとめどなく話して相手の話を一切聞かない点で変わっている。
「受動型」というのは、自分から話しかけたり関わりを持ったりすることはないのだが、一応は「人に合わせることができる」タイプのアスペルガー症候群である。しかし、自分からは決して人間関係を続けることはないので、相手のアプローチが切れればそれで終わる。
「孤立型」というのは、受動型のように周囲に合わせるということすらもできず、常に孤独の中にいる。自分の気持ちや感情を言うこともない。友人との付き合いもない。結婚もできないか、しても失敗する。
結局のところ、どのアスペルガー症候群も「人と合わせることができない」ので、遅かれ早かれ一緒にいる相手を驚かせたり、傷つけることになる。
実は、彼らの多くは大人になるにつれて、自分のおかしさを自覚するようになる。
そのため、社会で生きていくために、本当の自分をなるべく見せないように努力するようになる。本質的に自分を変えることができないので、できるのは「見せない」ことと「普通に見えるようにカモフラージュする」ということである。
ただし、決して普通になれないので、アスペルガー症候群の人はずっと「生きづらさ」を抱えて暮らしていく。当然、アスペルガー症候群の人の中には、当然「自分がそうだ」とは気づいていない人も多い。ただ「自分はどうやら人と感覚が違うようだ」と思いながら、違いを何とか隠して生きている。
アスペルガー症候群の子供は増えているのだが、理由は分からない。もしかしたら、あなたの身のまわりにもアスペルガー症候群の人がいるかもしれない。
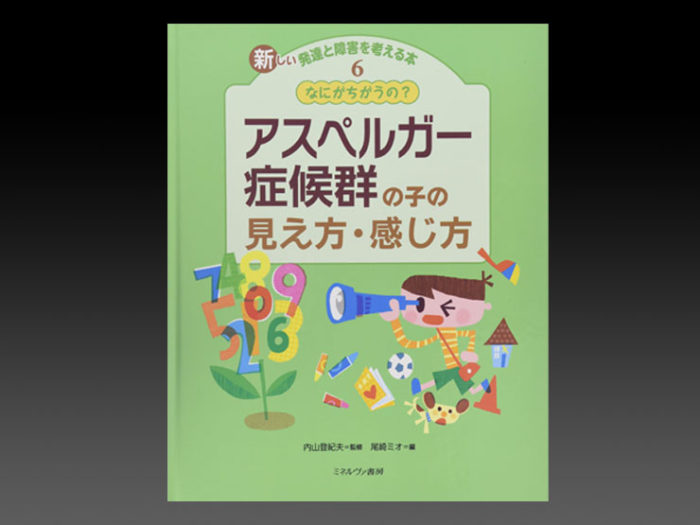




コメント
はーい、私のことです。ボッチ行動大好きです。一匹オオカミです。
「協調性がありません」と小学校入学時から高校卒業まで全ての担任に通信簿に書かれました。
授業を妨害するという事はなく、いつも窓の外を見ていました。
小学5,6年時の女の担任には徹底的に嫌われ無視されました。
主要科目の成績は良く、特に算数は良かったけれど体育がダメでした。
子供の頃は、軟体動物みたいと言われるほど身体が柔らかかったのもアスペの特徴らしいです。
友達はいませんでしたが、寂しいと思ったことがありません。
いつも自分の世界に浸って空想していて、その方がずっと楽しい。
傾城さんもアスペの傾向がないですか?
アスペの多い街に住みたいと思ってました。アメリカならテキサス州ヒューストンとか。
日本なら筑波学園都市あたりかな?
対人関係がうまくいかない、人とあわせるのがうまくない等、アスペルガーを自分の特性として仕事に
いかせれば、能力を大きく発揮するのではと思います
理系能力が高いのであれば研究職、こだわりが強いのであれば品質管理の部門等でしょうか
能力を生かしやすい学校や、職場環境が増えてくればよいのではと思います
空気を読む能力とハッタリだけで生きていける不動産業界は絶対ダメです(笑)
しかし「アスペルガー症候群」という言葉が、広く世間に認知されてきてよかったと思います
ひと昔前だと、「落ち着きのない子」「変な子」「空気が読めない子」で片づけられていましたから
実は私…この障害を持っています。。。
この事を記事にして下さった鈴木氏に深い感謝の意を表します。
私はグレーゾーンなのだそうです
脳の構造上、嫌なことをずっと忘れられず
ひたすら反芻してしまうのが辛いです
吉濱ツトムさんのyoutubeをよく見てます
とても明確にかつ簡潔にまとめられていてとても参考になりました。本質を的確に捉えていると思います。
傾城さんもアスペルガー症候群ですよね?
売春婦に対する異常なこだわりとか、
孤独な人生とか、
間違いないと思います。
それは違う感じがします。
傾城さんは後天的に行き着いた先の世界の住人になっただけと思います。
数年前に心療内科でこれ言われた事ありますね、アスペルガーに近いって。
決定的なものがなかったらしく、そうと断言されたわけじゃないですが。
ただ、幼年期を振り返るとわかる気がします。
得意分野では異様な能力を発揮してました。(私の場合は将棋とか対戦系のゲームとかでしたが、学校内で負け知らずでした。今でも格ゲーや将棋はそれなりにやってるつもりです。……本気で将棋やりこんでたら、奨励会とかに入れたのかなぁw)
確かに小中学校の頃は相当な問題児でしたし、周りに合わせるってこと全く出来ませんでしたから。
しかし感受性が強いので、話を聞いてると相手の痛みや悲しみ、怒りなどにも共感してしまうことも少なくないです。
プライベートに入り込まれるのは好きじゃないですね。
ただ、異性同性問わず好意を持ってる人となら、休みの日は一緒にいたり食事にいったり温泉いったりとかするのは好きです。