
社会環境は悪化しており、誰もが生きにくい社会と化している。これは政権が変わったら解決するわけではない。これからもずっと弱者が切り捨てられる傾向が続いていく。場合によっては、非人道的なまでに弱者が切り捨てられる社会となる。弱者が苦しむ社会が続いていく。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。著書は『ボトム・オブ・ジャパン』など多数。政治・経済分野を取りあげたブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」を運営、2019、2020、2022年、マネーボイス賞1位。 連絡先 : bllackz@gmail.com
必死にもがいても地獄に落ちていく
日本政府は30年にもわたって日本を成長させることができず、少子高齢化も解決できず、あげくの果てに国民負担率をどんどん引き上げてきている。税金と社会保険料は上がる一方で下がることはない。
今後も、この政府の姿勢は変わらないだろう。今の与党が崩壊して政権が取れそうな野党に変わったところで、その野党もまた増税を主張しているのだから、政権交代したところで何も変わらない。
今の政治家・官僚たちは、「景気が低迷しようが困窮者が飢え死にしようが、とにかく何があっても国民から税金を取る」という決意をしているように見える。
最近はちらほらと「消費税は15%になるのではないか」「最終的には19%を目指すのではないか」とも噂されている。
将来的に確約されているのは、税金は高くなっていき、福祉は削られていくという現実である。すでに年金の削減は微細ながらも少しずつおこなわれているし、医療の自己負担も負担額が上昇している。
しかし日本政府は、少子高齢化という社会を自滅させる要因を真剣に解決しようとしないので、この状況を好転させることができない。
問題を放置して対症療法をしていても、一時的にはなんとかなっても遅かれ早かれ問題はさらに深刻化してぶり返す。アリ地獄に落ちたアリのように、必死にもがいても地獄に落ちていくのをとめられない状況になっている。
日本の人口は約1億2,000万人だが、総務省の2023年10月の統計によると、高齢者人口は約3,622万人、総人口に占める割合は29.1%にまで上昇している。この割合は過去最多になっているのだが、もちろんこれでとまったわけではない。もっと高齢者人口の総人口に占める割合は増えていく。
インターネットの闇で熱狂的に読み継がれてきたカンボジア売春地帯の闇、『ブラックアジア カンボジア編』はこちらから
状況は良くなるよりも悪くなる
高齢者が働くといっても限度があるわけで、彼らの多くは年金生活に入り、年金がもらえない高齢者は生活保護に頼って生活することになる。生活保護受給者がうなぎ登りに増えているのも、貧困の高齢者が増えているからでもある。
物価上昇が続くと、さらに困窮する高齢者も増える。少子化なので現役世代の負担も増えて一緒に貧しくなる。政治はあいかわらず無能だ。そのため、生活保護という制度もいずれは立ちゆかなくなっていくだろう。
今の日本社会の人口構成や、政治情勢や、社会情勢を見ると、楽観視できるものは何もない。
状況は良くなるよりも悪くなる方向性にあるのは、人口動態のトレンドにそのまま直線を引いたら誰でも見えてくるはずだ。国連は「日本人は2100年には8,300万人にまで減少する」と推計を出している。
ただ人口が減るのではない。高齢化して人口が減るのだ。高齢化が進めば進むほど日本という国の活力は失われて仕事もイノベーションも消えていく。しかし、高齢化と人口減に歯どめをかけるものは何もない。
日本企業が弱体化していく中で、日本特有の雇用制度であった年功序列も終身雇用も成り立たなくなった。これを加速させたのは2000年代からおこなわれた非正規雇用者の拡大である。
政府側だった人間が、「正規雇用といわれるものはほとんどクビを切れないんです。クビを切れない社員なんて雇えないですよ、普通」といって、どんどん非正規雇用者を増やしていった。
日本企業は正社員を非正規雇用者に置き換え、従業員を使い捨てにするROE経営の企業が普通になっている。非正規雇用者は2023年の時点で2,124万人となっている。非正規雇用者比率も37.2%である。つまり、働いている人の約4割は、もう非正規雇用者なのだ。
「年々、生きにくい社会になっているのではないか」と日本人が思うのは錯覚ではない。成長しない国の中で、貧困層がどんどん増えてしまっている。非正規雇用者は「景気の調整弁」なので、景気が悪化したら真っ先に切り捨てられていく。
働く人の約4割は、雇いどめに遭ったり、雇われなかったり、いつクビにされるのかと不安な気持ちにまみれながら生きている。社会環境は急激に悪化しており、誰もが生きにくい社会と化している。
これからもずっと弱者が切り捨てられる傾向が続いていく。
1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから
弱者を切り捨てる時代に
これから非人道的なまでに弱者が切り捨てられる社会がやってくる理由は、すべてが複合的に絡まって同時並行で襲いかかってくるからだ。弱者は4つの存在から切り捨てられる。
「社会」が弱者を切り捨て、「国家」が社会を切り捨て、「企業」が弱者を切り捨て、「家庭」が弱者を切り捨てる。
「社会」にはどの時代にもその時代の空気がある。その空気の中には、弱者を大切にしようとする時代の空気もあれば、弱者を排除しようとする時代の空気もある。
理想主義の社会であれば弱者を大切にするような空気が芽生えるが、競争主義や拝金主義や利己主義の社会であれば、弱者よりも自分が大切だと思って、他人を顧みない空気となる。
現代社会は、資本主義が苛烈になるにつれて「金こそすべて」みたいな主義主張をするような浅ましい人間が増えて、弱者を負け犬と嘲笑い、踏みつけにするような社会となっている。弱者は社会から見捨てられた。
「国家」も財政赤字が膨らむと、福祉を削減するようになって弱者を切り捨てていく。「企業」もグローバル化による激甚な競争によってコスト削減を常に強いられ、弱者を見捨てて切り捨てていく。
そして、貧困が極まるにつれて「家族」の絆も切れやすくなり、家族の中の弱者を支えたり、面倒を見たりする精神的な余裕も経済的な余裕も失っていく。
高度成長期に何とか経済的に余裕を持った両親は、ニートや引きこもりの子供を養う余裕がある。だが、一歩間違えれば生活保護を受けなければならないような両親は、もはやニートや引きこもりの子供を養う余裕もない。
自分たちが弱者になるのだから、他の弱者の面倒を見ることができなくなってしまうのだ。みんなが弱者になるので、誰も助けられない。かくして弱者は、社会にも国家にも企業にも家族にも見捨てられて、いったんどん底に転がり落ちたら誰からの救済も受けられなくなる。
インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから
このように弱者は切り捨てられていく
現在は生きにくい社会となっている。事あればすぐに弱者が切り捨てられることになるのだが、どのような現象が進めば切り捨てられていくのか。以下のような現象が進めば、弱者は容赦なく切り捨てられていく。
・効率化・合理化が進むと、弱者が切り捨てられる。
・高度化が進むと、弱者が切り捨てられる。
・分業化が進むと、弱者が切り捨てられる。
・即戦力が求められると、弱者が切り捨てられる。
・専門化が進むと、弱者が切り捨てられる。
・拝金主義が進むと、弱者が切り捨てられる。
・利己主義が進むと、弱者が切り捨てられる。
・競争主義が進むと、弱者が切り捨てられる。
・社会が貧困化すると、弱者が切り捨てられる。
・社会の階級化すると、弱者が切り捨てられる。
文明の「進化」はとまらないが、進化が進むというのは文明がどんどん複雑化するということである。複雑化が進むということは、複雑な社会に対応できるだけの知力・能力・資金力が必要になっていくことを意味している。
生きるための難易度が上がっている。
なぜ、現代社会が莫大な弱者を生み出しているのかというと、こうした側面が複合的に進んでどれもとめることができないからだ。「切り捨て社会」なので、少しでも弱みがあれば、容赦なく蹴落とされる。
そうなると、貧困層は低賃金の労働しか残されていない。しかし、そんな低賃金の労働でさえも、今後は高度に発達していく人工知能(AI)や、ロボットが奪っていく。
これらの最先端技術のイノベーションのスピードは目覚ましい。これが自分の仕事を奪う存在であると実感している勤め人はまだほとんどいない。
これは、2000年代のグローバル化がなし崩しに進んでいた頃、自分の賃金が低下したり、リストラされていくと実感しなかったのと同じだ。気づいたときは、すでに手遅れになってしまっているのだ。
まじめに働いていても、ふとしたきっかけで弱者になっていく恐ろしい時代が待っている。そして、弱者に落ちると這い上がるのは容易なことではない。非人道的なまでに弱者が切り捨てられる時代がやってくる。




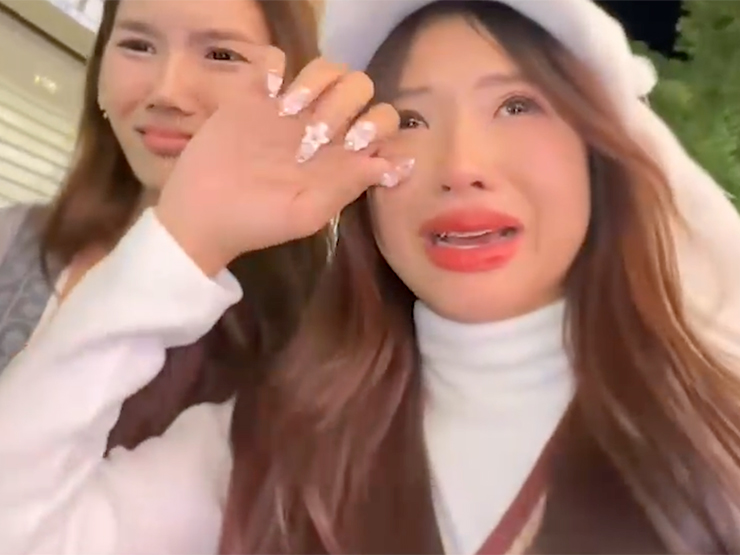
コメント
複雑な社会と言っても単に資本である優良企業の株式の
大量保有をすればいいだけですが
それにはかなりの現金がいるので
これは最も簡単であり最も難しいことです。